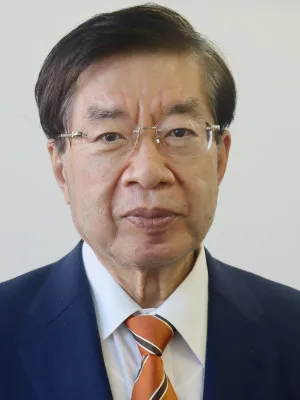2025-10-31 コメント投稿する ▼
再審制度の証拠開示、法制審で意見対立―限定案か拡大案か、袴田事件から43年の教訓
再審請求審における証拠開示の範囲をめぐって、法務省は「限定案」と「拡大案」の2案を提示しましたが、委員会の意見には大きな隔たりが生じています。 弁護士会側は、袴田事件の判決で認定された捜査機関による非人道的な取調べや証拠捏造の事実に基づき、「当初出されていなかった証拠で再審無罪になった事件がある」と指摘し、開示範囲を狭めることへの懸念を表明しています。
再審制度の証拠開示、法制審で意見対立―袴田事件の教訓が焦点に
法制審議会の刑事法部会は31日、刑事裁判の再審制度見直しを検討する第9回会合を法務省で開催しました。再審請求審における証拠開示の範囲をめぐって、法務省は「限定案」と「拡大案」の2案を提示しましたが、委員会の意見には大きな隔たりが生じています。1966年の静岡県一家4人殺害事件で55年ぶりに再審無罪が確定した袴田巌さんの事件を背景に、制度改革の方向性が決まる重要な局面を迎えています。
「無罪方向の証拠を検察が握ったままでは、えん罪被害者の救済が遠ざかるばかりだ」
「当初出されていなかった証拠で再審無罪になった事件がある。範囲を狭めるべきではない」
「再審は非常救済手続という性格から、証拠開示に厳格な基準が必要な場合もある」
「58年の長期化は許されない。迅速な制度構築が急務だ」
「検察官が判断する規定では、国民の信頼を得られない。独立した第三者判断が必要」
限定案が有力、弁護士会は強く反発―証拠隠蔽のリスク
法務省が示した限定案は、再審請求の際に元被告が示す「新証拠」と関連する証拠に限定する内容です。学識者を含む複数の委員から「これまでの裁判官の実務的な考え方に沿っている」という賛同の声が相次ぎました。しかし、同案については「現状よりも証拠開示の範囲が狭まる可能性がある」という指摘も法務省資料に記載されており、改善の余地が残されています。
これに対して、日本弁護士連合会の委員は強い反発を示しました。鴨志田祐美弁護士は会合終了後、「証拠を握っている検察官が判断することを許す規定」と限定案を批判し、有罪認定の根拠となった旧証拠や一定の類型に該当する証拠も含める「拡大案」の必要性を強調しました。弁護士会側は、袴田事件の判決で認定された捜査機関による非人道的な取調べや証拠捏造の事実に基づき、「当初出されていなかった証拠で再審無罪になった事件がある」と指摘し、開示範囲を狭めることへの懸念を表明しています。
袴田事件が露呈した制度の不備―29年待ったえん罪被害者
袴田巌さんは1966年に逮捕され、1980年に死刑判決が確定した後、43年10か月の長期間を経て、2024年9月26日に再審無罪判決を言い渡されました。驚くべきは、再審を求めてから無罪につながる決定的な証拠が開示されるまで、実に29年の歳月が必要だったという事実です。その間、袴田さんは身体拘束だけでも48年間、死刑囚として34年間の苦痛を味わいました。
静岡地裁の再審無罪判決では、血液が付着した「5点の衣類」や袴田さんの実家で発見されたとされるズボンの端切れなど、重要な証拠が捜査機関による捏造であることが認定されました。この判決から明らかなのは、現行の刑事訴訟法が再審手続について定める規定がわずか19か条しかなく、証拠開示に関する法的な基準がまったく存在しないということです。この制度の空白が、えん罪被害者の救済を長期にわたって遅延させる根本的な原因となってきたのです。
年度内答申、来年国会提出を目指す―法改正の行方不透明
法制審議会部会は、年度内に法改正に向けた答申案の作成を目指しており、法務省は来年度の通常国会への法案提出を想定しています。しかし、31日の会合でも委員の意見が平行線をたどったため、今後の議論の展開は不確定な状況です。部会が検討する論点は、証拠開示の範囲以外にも「証拠開示の弊害を検討する時点」「証拠の一覧表提出規定」「証拠を受け取る主体(裁判所か再審請求側か)」など、多岐にわたっています。
日本弁護士連合会は、再審法改正の早期実現を求める会長声明を発表し、年度内での答申取りまとめを強く主張しています。同連合会は、えん罪被害の深刻さと再審制度の実情を踏まえ、「法改正は一刻の猶予も許されない」と訴えており、法制審議会での年単位の検討時間の延長に強く反対する姿勢を示しています。制度改革の行方は、無罪を示す証拠が埋もれない実効性のある再審制度を実現できるかどうかの大きな試金石となります。